先日より国語の学習を兼ねて、書写しつつ、たろすけと詩を楽しむような時間を作っていました。
ある日、金子みすゞさんの『繭と墓』を読みました。蚕は繭の中に入り蝶になるけれど、人は墓に入り天使になるという内容です。
私は蚕の羽化、人が天使になる、その意味を考えると死を匂わす悲しい印象を抱きました。ところがたろすけにどう感じたか聞いてみると前向きな詩だと言います。
私と対照的な解釈だったので詳しく尋ねると、「蚕は繭に入り蝶に生まれ変わる。人も墓に入って天国へ行き違う生き物に生まれ変わる。だからこれは新しいものに変身する、嬉しいことを書いた詩なんだ」と教えてくれました。この回答に私はハッとさせられました。
昨年、我が家で飼っていたカブトムシやクワガタが死んでしまった時、死んだことがわかった時こそ悲しそうにしていたものの、別れを惜しむわけでもなく、すぐさま「お墓に入れよ」と土に埋めようとしていたたろすけを思い出しました。その様子を見て、私はあんなに喜んで飼っていた子達なのにさっさと始末しようとするなんて情がないのか!などと感じていました。
しかし、その詩の解釈を通して、たろすけの死生観、そして行動の意図が結びついたのです。死んでしまった虫達も、土に埋め供養することで生まれ変われるのだと信じていて、可愛がっていたからこそすぐにお墓に入れて新しい命に導いてあげたかったのだと。
そういえば、庭で虫を見かけるとたろすけは「このカマキリはカブトムシの生まれ変わりかな?会いにきたのかな」などと言っていました。そしてその度に私は「そーかもねぇ」と生返事をしていたことを思い出し、真剣な気持ちに応えなかったことに申し訳なくなりました。
大人から見るとなぜそうなんだ?と怪訝に思うことにも子どもなりの意味も考えもあるのだと改めて痛感し、目に見えている姿や行動で判断せず、内なる想いを見出していかねばと心付いた一件となりました。
– –
ところで、たろすけは物心がついた頃から虫が好きなので、虫を見つければ捕まえては飼いたがります。それで試行錯誤で飼ってみて、上手くいかずに死なせてしまうことも多々あり…。
そんな経験を重ねてたろすけも少しずつ虫の命について考えるようになったようです。それで、話し合って決めました。
- 捕まえた虫は図鑑で調べ、何を食べるのかを確認する
- 継続して最後まで用意していくことが難しい食べ物だったら飼わない
- 用意できても数日飼ってみて食べているところを確認できなかったら放す
- 飼うと決めたら毎日観察して世話をする
というようなルールで、虫と関わることに落ち着きました。
今でも捕まえはするけれど、「どうする?」と聞くと、飼えないと知っているものはその場で放す、生態がわからないものは「調べてみるから連れて帰っていい?」と言うようになり、闇雲に飼いたいと言っていた頃からの成長を感じられるようになりました。放してからも時折、「クサキリは今頃どうしてるかなー」などと思い出しては惜しんでますが…。
虫を扱う力の加減、飼育を通して自然について考えること、生き物の命を扱うことにはやはり図鑑では得難い知識以外の学びがあるように思います。今年の夏も昨年産んでもらったカブトムシ達を含め、命を見届けさせてもらうことになるかもしれません。
ちなみに、我が家のいわゆる害虫の類の扱いですが、庭では基本放置することにしました。植物は結構かじられて、ブルーベリーは今年根がダメになってしまいましたが…。まぁ、趣味の園芸なのでそこも含めて楽しむと言うことで。
家の中は、ここは我らの住むところだから…との理由で駆除しちゃいます。蜘蛛なんかは放っておきますが。
命についての教育は難しいものですね。


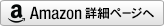

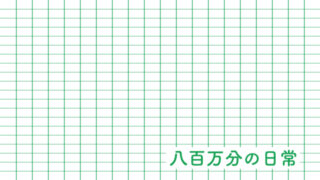
コメント